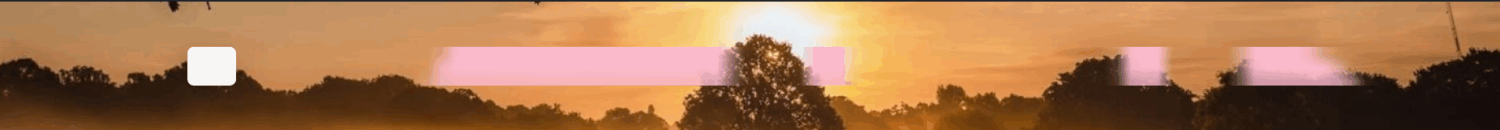コーヒーを淹れる時間は、儀式だ。
お湯の温度、注ぐ速度、蒸らす時間。
そのすべてをコントロールするために、僕はKalitaの銅ポットを使う。
使い込むほどに色が変わり、鈍い輝きを放つ。
これは、僕の時間を吸い込んで育つ道具だ。
Scene: 湯気の向こう側
銅は、熱伝導率が高い。
お湯を入れた瞬間、ポット全体が熱くなる。
持ち手には革を巻いてあるが、それでも熱が伝わってくる。
その熱さが、「今、お湯を扱っている」という緊張感を生む。
細く伸びた注ぎ口。
鶴の首のように美しいカーブ。
傾けるだけで、糸のようなお湯が出る。
湯麺が揺れない。
狙った場所に、一滴ずつ落とせる。
このコントロール性が、味の輪郭を決める。
Feeling: 変色という美学。
最初はピカピカだった。
でも今は、炎に焼かれ、お湯に触れ、飴色に変色している。
これを「汚れ」と呼ぶ人もいるかもしれない。
でも僕には、これが「景色」に見える。
毎朝、このポットでお湯を沸かしてきた。
その積み重ねが、この色を作った。
新品にはない威厳。
ただ置いてあるだけで、キッチンの空気が引き締まる。
Root: 道具に使われる喜び。
このポットは、手入れが必要だ。
濡れたままにすると、すぐに錆びる。
使い終わったら、すぐに拭き上げる。
面倒だ。
でも、その「手間」こそが、愛着の正体だと思う。
便利な道具は、人を怠惰にする。
良い道具は、人を律する。
毎朝、ポットを磨きながら、僕は自分の心も磨いているのかもしれない。
森で会おう。