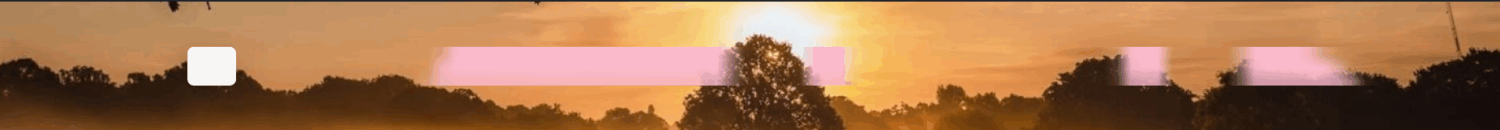氷点下の朝。テントのジッパーを開けると、凍てついた空気が肺の奥まで侵入してくる。
白い息を吐きながら、僕はザックのサイドポケットから「相棒」を取り出す。
白樺のコブから削り出された、ひとつのカップ。ククサだ。
手にした瞬間、指先に伝わるのは冷たい陶器の感触ではなく、じんわりとした温かみだ。
それはまるで、この木がまだ森の一部だった頃の記憶を、その身に宿しているかのようだ。
熱いコーヒーを注ぐ。湯気が立ち上り、木の香りがふわりと鼻腔をくすぐる。
カップを両手で包み込むと、コーヒーの熱が木肌を通して、ゆっくりと、しかし確実に僕の冷えた手を温めていく。
直接的な熱さではない。まるで生き物の体温のような、有機的な熱だ。
時間の化石
「この子は生きてるからね」
かつて、このククサを譲ってくれた老人が言った言葉を思い出す。
「使うんじゃない。育てるんだ」
その言葉の意味が、今なら少しわかる気がする。
手に入れたばかりの頃、この肌はもっと白く、頼りなかった。
けれど、幾度ものキャンプを共にし、コーヒーを飲み、スープを啜り、その都度オイルを塗り込んできた。
焚き火の煙に燻され、僕の手の脂を吸い、雨に濡れ、風に乾かされた。
今、飴色に輝くその表面に見えるのは、単なる汚れではない。
僕たちが共有してきた「時間」そのものだ。
傷のひとつひとつが、あの日の岩場の記憶であり、あの夜の語らいの痕跡だ。
これはもはや道具というよりも、僕という人間の歴史を記録した外部記憶装置――時間の化石なのかもしれない。
森との同化
森の中でこのカップに口をつける時、僕は奇妙な感覚に襲われる。
唇に触れる木の質感。口の中に広がるコーヒーの苦味。
その境界線が曖昧になり、自分が森の一部に溶け込んでいくような感覚。
かつて白樺の木の中に流れていた水脈と、僕の血脈が、このカップを通して繋がっているような錯覚。
僕は木の命とキスをしている。
そう思うと、背筋が少し粟立つような、それでいて深い安らぎにも似た感情が胸を満たす。
所有する、ということの意味を問い直す。
店でお金を払えば、商品は手に入る。けれど、それは本当の所有ではない。
時間をかけ、手間をかけ、相手(モノ)の性質を理解し、自分の生活の一部として馴染ませていく過程。
その緩やかな同化のプロセスを経て初めて、モノは「僕のもの」になる。
いや、もしかすると僕の方が「モノの一部」になっているのかもしれない。
このククサがなければ、今の僕のキャンプという営みは成立しないのだから。
飲み干したカップの底に残る、黒い澱を見つめる。
また一つ、記憶が層になって重なった。
帰り道、ザックの中でカトコトと鳴るその音さえも、僕には心地よい子守唄のように聞こえた。