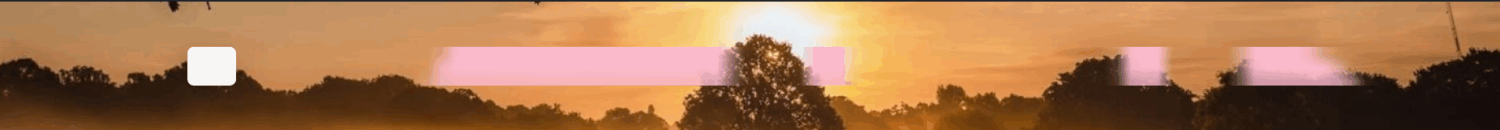陽が落ち、森が深い藍色に沈む頃、焚き火に火を入れる。
最初は小さな種火が、やがて枝を舐め、薪を捉え、力強いオレンジ色の柱となって闇を押し返す。
薪が爆ぜる音。パチッ、という鋭い破裂音の後、炎が不規則に揺らめく。
僕たちは長いこと、何も喋っていなかった。
だが、そこに気まずさは微塵もない。
共有される空白
街での生活において、会話の途中の沈黙は「空白」だ。
何か気の利いた言葉で埋めなければいけない、焦燥感を伴う隙間。
相手が退屈しているのではないか、怒っているのではないか、と顔色を伺ってしまう。
けれど、焚き火の前での沈黙は「共有」だ。
僕たちはただ、同じ炎を見つめている。
変幻自在に形を変える炎のダンス。芯の赤熱した部分の脈動。
その圧倒的な原始のエネルギーを前にして、言葉など無力だ。
僕の視線と、君の視線が、炎という一点で交差する。
言葉を介さずに、意識だけが煙のように混ざり合っていく。
魂のチューニング
炎を見つめていると、不思議と自分の内面にある澱のようなものが溶け出していくのを感じる。
昼間の些細なトラブル、明日への不安、社会的な仮面。
そういったノイズが、熱によって浄化され、灰になって空へと昇っていく。
残るのは、飾り気のない素っ裸の魂だけだ。
隣にいる君も、きっとそうなのだろう。
普段は言えないような弱音や、ずっと胸に秘めていた夢。
そういった「本当のこと」が、ふと口をついて出る。
あるいは、何も言わなくても、ただ隣に座っているだけで、互いの存在を肯定できる。
「暖かいね」
誰かが小さく呟く。
「そうだね」
それだけのやり取りで、十分だった。
言葉は本来、これくらい少なくていいのかもしれない。
炎は、僕たちから余計な言葉を燃やし尽くして、最後に残った真実だけを見せてくれる。
薪をくべる。火の粉が舞い上がる。
僕たちの夜は、まだ長い。