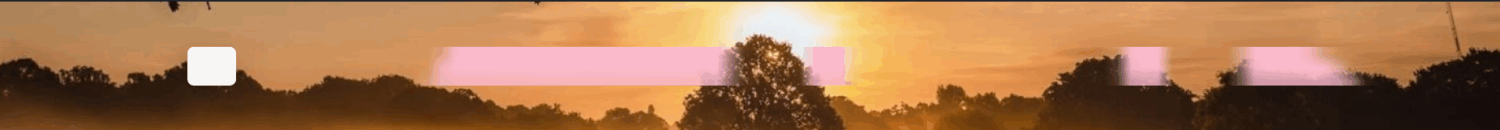毛布を纏う、という儀式。
冬の夜、森の小屋に一人でいる。
外は氷点下。
窓の向こうで、木々が風にざわめいている。
焚き火を消したあとの静寂の中で、僕はウールの毛布を肩にかける。
ずしりとした重みが、肩に降りてくる。
それは、誰かに抱きしめられたような安心感だった。
Scene: 羊の記憶
ウールは、羊の毛だ。
生きていた動物の体温を保つために、何千年もかけて進化してきた素材。
その繊維には、微細な空気の層が無数に閉じ込められている。
だから、温かい。
化学繊維のように「熱を閉じ込める」のではなく、「呼吸しながら保温する」。
湿気を吸収し、外に逃がす。
身体が蒸れない。
まるで、羊が草原を歩いていた頃の風を、今も覚えているかのように。
Feeling: 重さは、優しさ。
この毛布は、軽くない。
持ち上げると、ずっしりとくる。
でも、その重さがいい。
身体全体に、均等に重みが分散される。
まるで大地に引っ張られるように、深く沈んでいく。
そして、眠りが訪れる。
科学的には「圧迫刺激がセロトニンを分泌させる」というらしいが、
僕にとっては、もっと単純な話だ。
「包まれている」という実感が、孤独を和らげる。
Root: 道具は、いつか土に還る。
化学繊維の毛布は、いつか必ずゴミになる。
でも、ウールは違う。
これは、土に還る。
使い終わったら、庭に埋めればいい。
やがて微生物に分解され、土壌を豊かにする。
循環の中に、僕たちも生きている。
「買う」ということは、「自然から借りる」ということだと思う。
そして、いつかちゃんと返す。
それが、生き物としての礼儀だろう。
森で会おう。