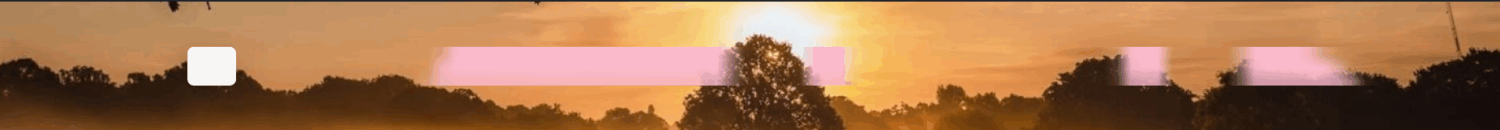夜が深まると、森は本来の姿を取り戻す。
圧倒的な闇。その中で、僕の手元にあるのはフュアーハンドランタンの小さな灯りだけだ。
マッチを擦る。
シュッ、という音と共に、硫黄の匂いが鼻をかすめる。
芯に火が移り、ガラスのホヤの中で炎が呼吸を始める。
LEDの光は「照らす」ためのものだ。
でも、このオイルランタンの光は「共にいる」ためのものだと思う。
風が吹けば揺らぎ、燃料が減れば小さくなる。
その不完全さが、どうしようもなく愛おしい。
炎を見つめていると、時間は意味を失う。
ただ、パチパチという音と、温かいオレンジ色の光があるだけ。
僕はマグカップを両手で包み込み、その温もりを感じながら思う。
人間が太古の昔から見つめてきたのも、きっとこんな夜だったのだろうと。
小さな太陽を一つ、手元に置く。
それだけで、孤独は恐怖ではなく、静かな友人に変わる。