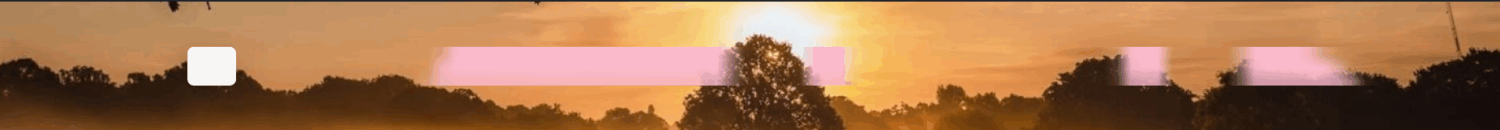森に夜が訪れる音がする。 枯れ葉を踏む風の音。遠くで鳴く鹿の声。 そして、目の前でパチパチとはぜる焚き火の音。
スイッチひとつで世界中が明るくなる時代に、僕はわざわざ暗い森へ入り、マッチを擦る。 今日、僕の横にあるのは、ドイツ生まれの無骨な相棒、フュアーハンドランタン 276。
この頼りない、けれど温かい灯りの下にいると、 普段いかに自分が「明るすぎる場所」で、大切なものを見失っていたかに気づかされるんだ。
便利さの中で失った「闇」
僕たちの日常は、光に満ち溢れている。 オフィス、コンビニ、そしてスマートフォンの画面。 白いLEDの光は、確かに便利で、安全で、効率的だ。
けれど、その光は「影」を許さない。 すべての隅々まで照らし出し、「さあ、見ろ。さあ、動け」と僕たちを急き立てる。
森に入ってランタンに火を灯すと、そこには圧倒的な「闇」が残る。 ランタンの光は、半径1メートルほどしか照らさない。 その先は、深い深い夜の森だ。
でも、その「見えないこと」への恐怖が、いつしか「守られている」という安堵に変わる瞬間がある。 限られた光の中だけで、今は生きればいい。 そう許されたような気がするからかもしれない。
手間という名の休息
このランタンは、ただの道具ではない。 それは、ある種の「儀式」を要求する生き物だ。
タンクにオイルを注ぐ時の、とくとくという音。 芯(ウィック)の角をハサミで切り揃える、繊細な作業。 そして、ホヤ(ガラス)を持ち上げ、火を移す一瞬の緊張。
これらすべての「手間」が、僕にとっては深呼吸と同じ意味を持つ。
LEDランタンなら、ボタンを押すだけで終わる。0.1秒だ。 でも、フュアーハンドと向き合う時間は、5分、10分とかかる。
その時間の無駄遣いこそが、現代人にとって最高の贅沢なんじゃないだろうか。 手を動かし、道具を愛でる。 その単純な反復作業の中で、ざわついていた心が少しずつ鎮まっていくのを感じる。
揺らぐ炎、不完全な美しさ
フュアーハンドの炎は、決して一定ではない。 風が吹けば揺らぎ、オイルが減れば小さくなる。 その「不完全さ」が、どうしようもなく美しい。
じっと見つめていると、炎のリズムが心拍とシンクロしていくような感覚に陥る。 1/fゆらぎ、というらしいけれど、理屈はどうでもいい。
ただ、この炎を見ていると、 「完璧でなくてもいいんだよ」 「揺らいでいても、燃え続けていればいいんだよ」 と、肯定されているような気持ちになる。
ジンク(亜鉛メッキ)の肌触りは、冷たくてざらついている。 使い込むほどに鈍く輝き、煤(すす)で汚れていく。 その傷跡の一つ一つが、僕とこいつが過ごした夜の記憶だ。
結論:闇を愛でるための相棒
もし君が、日々の眩しさに疲れてしまっているなら。 一度、すべてのスイッチを切って、小さな火を灯してみてほしい。
フュアーハンドランタンは、闇を消し去るための道具じゃない。 闇と共存し、夜の深さを楽しむための相棒だ。
この淡い光の下で飲むコーヒーは、 どんな高級カフェのそれよりも、深く、甘い味がするはずだよ。
それじゃあ、また森で会おう。