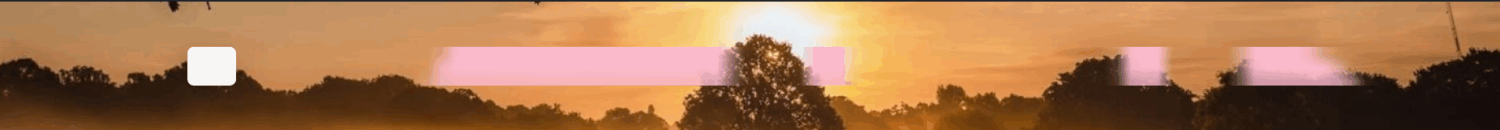削れば減る。だからこそ、その線は尊い。
ボールペンのインクが切れる瞬間は、唐突で無機質だ。
だが、鉛筆は違う。
書けば書くほど、確実に短くなっていく。
俺の思考を紙に写し取る代わりに、自らの身を削る。
その潔さに惹かれて、俺はBlackwing(ブラックウィング)を使う。
かつてスタインベックも愛用したという、伝説の鉛筆だ。
Scene: 杉の香りと黒鉛の粒子
独特の長方形の消しゴムがついた、美しいフォルム。
ナイフでゆっくりと削っていく。
シダーウッド(杉)の香りがふわりと立ち上る。
それは森の匂いだ。
芯を尖らせ、紙に走らせる。
他の鉛筆よりも濃く、滑らかな書き心地。
「サラサラ」というより「ヌルヌル」に近い。
力を抜いていても、黒鉛が紙の凹凸にしっかりと食い込んでいく。
この感触は、デジタルペンでは絶対に再現できない。
Emotion: 儚さを愛でる
間違えたら消しゴムで消す。
完全に消えるわけではなく、うっすらと跡が残る。
その痕跡さえお、思考のレイヤーだ。
そして、使い続けるうちに、鉛筆は短くなり、最後は持てなくなる。
補助軸を使って、ギリギリまで使う。
その「終わりがある」という事実が、書くことへの集中力を高める。
永遠ではないからこそ、今、この瞬間に書き留める言葉に魂が宿る。
Root: アナログへの回帰
便利な道具は、時として人間の感性を鈍らせる。
不便で、手間がかかり、消耗する。
そんな鉛筆というツールが、俺たちに教えてくれること。
それは「命あるものは、すべからく滅びる」という諸行無常の理(ことわり)かもしれない。
短くなった鉛筆を並べて眺めると、自分がどれだけ思考してきたかのログになる。
チビてしまった相棒に感謝を込めて。
また新しい一本を削り始める。
森で逢おう。